|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
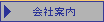
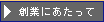
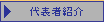
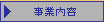

|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
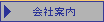
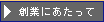
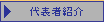
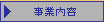

|
||||||||
|
創業にあたって 20世紀末を迎え、現在の日本は政治・経済・社会を含めすべて面で行き所のない閉塞状況に陥っている。出版業界も例外でなく、書籍はもちろん雑誌までここ数年は前年度割れが続き、毎年数冊は出ていたミリオンセラーもここ1〜2年は生まれていない状況である。その原因は情報伝達という点から見ると、紙媒体以外のさまざまな情報源の存在で消費者の選択肢が広がったこと、特にインターネットの驚異的な普及により情報伝達の手段が大きく変化してきたことによる。わざわざ紙を媒体として使用しなくとも、より速く有効な手段が新しく生まれてきたということである。ただ、果たして紙媒体は衰退して行くのみなのだろうか。 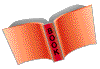 古代パピルスの発明以来2000年余り、どのような新しい媒体が出現しようと、紙は人間の一番身近な情報伝達の手段としてその地位を守り続けてきた。その優位性は活版印刷術の発明によりますます高まり、より多くの人々の支持を受け、その役割を全うしてきたのである。それは、近代における映画の勃興やテレビの普及にも拘わらずに、である。 確かにインターネットの普及は驚異的で情報伝達性には優れているが、紙の携帯性や視覚性、利便性からは劣っている。それ以外、現在メディアと称されるものはテレビを始めラジオ、映画、ビデオなど数あるがそれぞれ特徴が異なり、上手に棲み分けをしている。 では、どうしてここ何年も出版界の不況が叫ばれて久しいのか。第一には日本国内全体が不況の嵐に包まれる中、出版界もここ数年は売上も実売率も前年度割れの状態が続いており、可処分所得の低迷が個人の遊興費の削減につながり、それによって本を購入する機会が減少しているのである。  その上、ダイエーやJR東日本1社の売上高と同じくらいの出版業界のパイの中で、出版業界の売上の6〜7割は、戦前か戦後まもなく設立され、活字に飢えた時代に大きく成長した老舗の大手出版社が占有している。出版点数もまた同様で、それらの大手出版社は好むと好まざるとに関わらず、自社の経営のために絶え間なく数多くの出版物を生み出していかなければならない。まず売上ありき、そしてそのための出版点数ありきである。そこには読者の嗜好より、安直に利益に結びつく企画が優先しているように見受けられる。つまり本を生み出すシステム自体が脆弱になっているわけだ。 したがって価値の多様性が叫ばれて以来、よほどのことがない限りマスの読者などは存在しない中で、このシステムを続けていけば、出版業界はますます衰退していくことは明白である。いまやインターネットに接続すれば月々1000〜2000円でありとあらゆる情報が手に入る状況で、もはや情報の垂れ流しだけでは出版は成立しなくなっている。いまこそ紙の媒体の特性を活かした付加価値の高い、普遍性のある企画こそが求められている。具体的には、絶えず読者の嗜好を迅速にそして詳細に分析し、ニッチ(隙間)を探し深く掘り起こすような企画こそが、まさにこれから求められていくのである。多様性が定着した時代だからこそ、ますますこの傾向は強くなるに違いない。 ところが、これまでニッチ(隙間)を探し出し、深く掘り起こすような企画は「専門書」という範疇でくくられ、出版業界の中では地味で特殊な存在として扱われてきた。つまり専門性が高く難解で、少ない読者しか想定できず、したがって市場も狭く高価にならざるを得なかったわけである。しかし、インターネットが爆発的に普及する現在、本当に少ない読者しか想定できないのだろうか。前述したように情報収集という意味では、活字以外にも多くの媒体が存在する。しかし、だからこそ活字の優位性を活用するコンテンツでさえあれば必ず、これまで以上の読者を獲得できると確信する。これまでの「専門書」は小部数を出版することによって、希少価値を誇り生き残ってきたが、それは当初から、ある一定の読者しか想定しなかったマーケティングである。つまり、本当は読者の広がりが期待できそうなテーマであるにもかかわらず、潜在的読者がその本の存在自体を知らない状況がこれまで続いてきたのである。 しかし今やネットの普及により、安価な告知方法がぞくぞく登場している時代である。ホームページやネット通販など、読者の目に触れる機会は圧倒的に多くなっている。だからこそ、これまで「専門書」と呼ばれてきた書籍を、もう一度その分野に関心を持っている読者にアピールしていけば、より広い購買層が広がるはずである。 またこれまで、堅実な読者はいるにもかかわらず、一定部数を印刷しなければ採算が取れないという製作単価の問題で、世に出なかった企画は数多くある。そこにはこれまで障壁になってきた原価計算上の問題が存在するが、それをクリアできる状況がここ数年整ってきたのである。つまり制作現場ではDTP化という大きな変化が起こり、大幅に制作費が圧縮された結果、これまで小部数では単価が高くなり、原価計算上不可能であった「専門書」出版が可能になったわけである。具体的には、これまで印刷所が行ってきた組版作業を出版社内で行うことにより、20%以上の制作費が削減されたのである。ただ、このDTP化によるスキルは一朝一夕でできるものではなく、編集担当者がDTPで多くの種類の単行本を手がけることにより、実現が可能になるものである。  一方でこの問題は逆説的な意味も含んでいる。不況の中で生き残りを図ろうとする場合、本来なら出版社(メーカー側)は全体的に経営問題を見直さなければならないが、これまでは直接制作費の削減ばかりを行ってきた。それによって、1円でも安い用紙を使用し、印刷経費も可能な限り圧縮してきたのである。それが読者にとって、出版界にとって本当によいことなのであろうか。どの本も同じようなイメージを与え、“金太郎飴”書店における“金太郎飴”本の販売につながり、ますます本が売れなくなるという落とし穴に、はまって行ったということも考えられるのである。 また少しでも見栄えをよくするために、原稿が少ない場合には活字を大きめにし、行間をあけ、ページ数をなるべく多くしようとし、原稿が多い場合は活字を小さめに行間を狭く、なるべくページ数を少なくするという、読者を無視したご都合主義が、本離れを引き起こした一因であるかもしれない。 このように、メーカー側には本来あるべき全体的な経営努力もなく、消費者のみにつけをまわしてきたことが、出版不況の大きな原因であると考えられる。メーカーとしては、もう一度紙の媒体の特性を分析し、何が他のメディアと異なるのか、どうやって差別化を図っていくのかを、研究しなければならない。特にWebメディアとの差別化を図らないと、紙の媒体の生き残りはますます困難なっていく。  当社では、Web上の限られたスペースの冷たい画面では不可能な、活字における書体、級数、組み方、また紙の色味や質感なども合わせて十分に吟味・研究しながら、読者にとって本当に読みやすく、楽しめる、ためになる、癒されるというテーマで、本作りに生かしていきたいと考える。 また当社の特徴として、手間のかかる執筆者の選定や執筆交渉、原稿依頼、原稿整理、その他取材の手配やテープ起こし、原稿割り付け、校正、組み版、DTPデータ作成まで、あらゆる企画・編集・制作業務に対応できる「トータルパブリッシングシステム」を構築している。したがってクライアントにとっては、この「トータルパブリッシングシステム」を利用すれば、編集と制作を分割して委託するより、管理上の手間が少なく済む上に、経費的にも削減できる。そして、これまで20年の書籍編集経験から培った編集制作スキルで、スムーズに、迅速に、そして安心して、気持ちよく委託できるようなシステム環境が整っている。つまり当社は、煩わしい編集制作実務をすべてフォローしながら、1冊の書籍を創造するトータルな仕事を手がける出版OEM企業として、大いなる発展を目指している。  最後にDTPによる出版データのデジタル化はコンテンツのあらゆる媒体での展開を可能にする。紙の媒体だけではなくCD−ROMやインターネットなどあらゆる媒体にコンテンツとして流通させることにより、利益をあげていくことも視野に置いていく。当社も紙の媒体で蓄積したコンテンツをネットで流通させ、紙媒体では味わえない動画や音声、写真などを添付し、付加価値つけて販売する。さらに言えば、ここではこれまでは認可事業だった“放送”という媒体も、ネットで動画と音声を流せば可能になり、出版社が自らのコンテンツを番組として活用し、ネット放送局になることも可能なのである。つまり、出版社とか放送局だとかという境界はもはや存在せず、“パブリッシャー(発信者)”として事業展開できるということである。 当社の提携会社には、パソコンソフトの開発・販売やCD−ROMの制作・販売、ホームページの構築、ネット環境開設事業などIT周辺事業を展開して実績を上げている会社があり、その面からも他社との競争でも安価で優良なシステムを構築でき、優位に立てる環境が揃っている。したがって当社は取次・書店やインターネットなど多くのルートを通して、アナログ・データ(文字)とデジタル・データ(画像・音声)両方を販売する“ゼネラル・パブリッシャー(総合発信者)”としてアピールしてゆきたい。 |